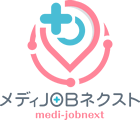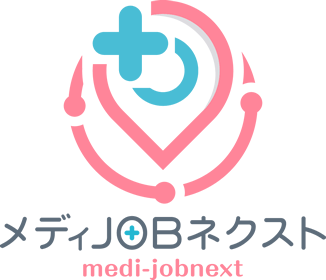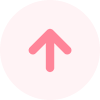2025/07/10
定年制度、再雇用、勤務延長の違いを整理!転職前に知っておきたい基礎知識
求人票の「定年制度」、気にしたことありますか?
「次こそは、腰を据えて長く働きたい」
――そう考えて転職先を探す方は少なくありません。
そんなとき、ぜひ確認しておきたいのが『定年制度』です。
求人票には、給与や休日だけでなく、定年に関する情報が記載されていることがあります。
ところが、「定年はどこも同じだろう」と思って見逃してしまうと、実は定年がなかったり、再雇用に条件が付いていたりというケースもあり得ます。
だからこそ、転職活動の段階で定年制度を確認しておくことは、とても重要です。
実はひとくちに「定年制度」といっても、企業によってその内容はさまざま。
このコラムでは、そんな定年制度についてわかりやすく解説していきます。
「正直、あまり知らなかった…」という方も大丈夫。
ぜひ最後まで読んで、納得のいく職場選びにお役立てください。
定年とは?
定年制の定め方
65歳まで働ける「高齢者雇用安定法」とは?
勤務延長制度と再雇用制度の違い
定年の現状は?
まとめ
定年とは?
定年とは、会社で働く人が一定の年齢に達したときに、いったん今の働き方を終えるルールのことです。
多くの企業では「60歳定年」が一般的ですが、最近では「65歳定年」にしているところや、「定年なし」という会社も出てきています。
ただ、「定年=仕事を辞めなければいけない」というわけではありません。
定年を迎えたあとも、会社によっては再び契約を結んで働き続けられる「再雇用制度」や「勤務延長制度」が用意されていることがあります。
定年制の定め方
企業が導入する「定年制度」には、いくつかの定め方があります。
最も一般的なのはすべての従業員に共通する「一律定年制」ですが、職種ごとに異なる定年年齢を設けるケースや、その他の柔軟な運用方法も見られます。
ここでは代表的な3つの定め方を紹介します。
一律定年制
すべての従業員に対して、同じ年齢で定年を設定する方法です。
たとえば「60歳定年」や「65歳定年」などがこれにあたります。
職種や役職、雇用形態に関係なく、一定の年齢に達した時点で退職する仕組みです。
職種別に定める
業務の特性や安全上の理由などから、職種ごとに異なる定年年齢を設ける方法です。
たとえば、現場作業職は60歳、事務職や専門職は65歳というように、職種ごとに柔軟に設定されます。
その他(定年制なし・役職定年制 など)
一部の企業では、そもそも定年制度を設けていない(定年制廃止)、または役職にだけ定年を設定する「役職定年制」など、独自の運用をしている場合もあります。
65歳まで働ける「高齢者雇用安定法」とは?
多くの会社では定年を60歳に設定していますが、実は「65歳まで働ける」ように定めた法律があります。
これが「高齢者雇用安定法」です。
日本では少子高齢化が進み、働く人の数が減少しているため、企業が高齢の方を雇い続けることがとても重要になっています。
そこで、この法律では、企業に対して65歳まで働けるようにすることを義務付けています。
具体的には、以下が求められています。
- 定年を65歳まで引き上げる
- または定年後も働き続けられる「再雇用制度」や「勤務延長制度」を設ける
この法律のおかげで、多くの企業が高齢の方でも働きやすい環境を整えているのです。
さらに最近では、70歳まで働けるようにする努力も企業に求められており、定年後の働き方がより柔軟になってきています。
勤務延長制度と再雇用制度の違い
高年齢者雇用確保措置として、多くの企業が「勤務延長制度」または「再雇用制度」を導入しています。
どちらも定年後の雇用を継続するための制度ですが、雇用形態や労働条件の扱いに明確な違いがあります。
勤務延長制度とは?
勤務延長制度とは、定年を迎えても、そのまま現在の雇用契約を延長して働き続ける仕組みです。
たとえば、正社員として雇われていた場合、その雇用形態を変更せずに60歳以降も勤務を続けることになります。
退職という手続きを挟まないため、雇用契約が途切れずに継続されるのが特徴です。
労働条件(職務内容や給与、待遇など)は基本的に定年前と同様であることが多いですが、企業によっては役職の変更や労働時間の短縮などが行われることもあります。
この制度は、業務の継続性や人材確保の観点で有効ですが、人件費の負担が続く点を課題とする企業もあります。
再雇用制度とは?
再雇用制度は、定年で一度退職した後に、新たな雇用契約を結び直して働く制度です。
多くの場合、定年時に正社員を退職し、再雇用後は契約社員や嘱託社員として再スタートします。
この制度では、労働条件が見直されるのが一般的で、給与の引き下げや勤務時間の短縮などが行われることがあります。
雇用は有期契約(たとえば1年更新)とされるケースが多いです。
定年の現状は?
では、実際にどのような制度が現場で採用されているのでしょうか。
ここでは厚生労働省が実施した「令和4年就労条件総合調査」の結果から、定年制度の現状を紹介します。
令和4年の調査によると、企業(常用労働者30人以上)における定年制度の状況は以下のようになっています。
定年制度を設けている企業の割合:94.4%
「一律定年制(全従業員に共通の年齢)」を採用している企業:96.9%
定年年齢の分布:
- 「60歳」:72.3%(依然として主流)
- 「61~64歳」:2.6%
- 「65歳以上」:24.5%(年々増加傾向)
勤務延長制度・再雇用制度の実施状況
- 「勤務延長制度のみ」:10.5%(年々増加傾向)
- 「再雇用制度のみ」:63.9%(依然として主流)
- 「両制度併用」:19.8%
まとめ:定年制度の違いを理解して、自分に合った職場選びを
定年制度、再雇用制度、勤務延長制度——
ひとことに「定年」と言っても、企業によって仕組みはさまざまです。
現在は多くの企業が「60歳定年+再雇用制度」を導入していますが、65歳定年や勤務延長制度、さらには70歳まで働ける制度を設けている会社も増えてきています。
転職を考えるとき、給与や勤務地だけでなく、「いつまで・どのように働けるか」も重要なチェックポイントです。
求人票にある定年や継続雇用の欄にもぜひ目を通してみてください。
自分の働き方や将来のライフプランに合った職場を見つけるために、今回のコラムが少しでも参考になれば幸いです。
参考文献
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
転職コラムのおすすめ記事
-
2024/06/18
面接の心得!成功のための基本ポイントを解説
-
2024/08/10
転職で人材紹介をつかうメリットとは?具体的な利用方法を解説!
-
2024/06/25
履歴書の書き方を解説!就活・転職で成功するための具体的な手順とポイント
-
2024/07/04
面接での自己紹介、成功するための完全ガイド!具体例あり