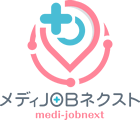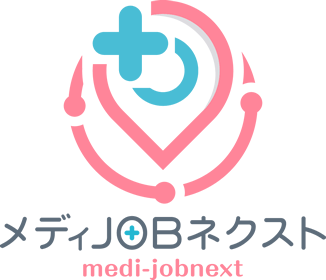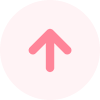2025/06/24
通勤手当は会社によって異なる!知っておきたい基礎知識を解説
転職時に確認しておきたいポイントのひとつが「通勤手当」です。
職場が徒歩圏内であれば気にする必要はありませんが、公共交通機関を利用する場合や車通勤が必要な場合には、通勤手当の有無や支給条件が働き方や家計に大きく影響します。
実は、この通勤手当、支給の有無や金額は会社によって大きく異なるのが現実です。
そこでこの記事では、通勤手当の基礎知識をわかりやすく解説します。
公共交通機関や車での通勤を予定している方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
通勤手当の支給は義務ではない
通勤手当の支給金額の相場
交通手段によって変わる金額
通勤手当には非課税限度額がある
通勤手当は社会保険料の計算対象
まとめ
通勤手当の支給は義務ではない
「通勤手当=必ず支給されるもの」と思われがちですが、実は通勤手当の支給は法律で義務付けられているわけではありません。
通勤手当とは、従業員が通勤のためにかかる費用を会社が補助する制度で、企業が就業規則等に基づいて任意で支給している手当です。
支給の有無や金額、対象となる交通手段、上限額などは、企業ごとに大きく異なります。
たとえば、
- 公共交通機関の定期代を全額支給する企業
- 月額上限を設けて一部のみ支給する企業
- 自動車通勤に距離に応じた手当を設定する企業
- そもそも通勤手当を設けていない企業
など、対応はさまざまです。
そのため、転職活動や入社前の段階で、通勤手当の有無だけでなく、支給条件や金額、対象範囲までしっかり確認することが重要です。
通勤手当の支給金額の相場
通勤手当は多くの企業で支給されていますが、その支給額には上限が設けられていることが一般的です。
企業側のコスト管理や税制上の非課税限度額との関係から、無制限に支給されるケースは稀です。
実際の上限額は企業によって異なりますが、よく見られる相場としては、
月額3万円〜5万円程度
を上限として設定している企業が多く見受けられます。
中には、非課税限度額にあたる月15万円(公共交通機関の場合)まで支給する企業もありますが、これは一部の例外的なケースです。
特に、勤務地が都市部から離れている場合や、自宅からの距離が長い場合には、上限を超えた分が自己負担になる可能性もあるため、あらかじめ支給条件を確認しておくことが重要です。
交通手段によって変わる金額
通勤手当の支給額は、利用する交通手段によって計算方法が異なります。
以下に代表的なケースを紹介します。
電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合
最も一般的な方法として、通勤経路における最安ルートの定期券代が基準となります。
通常は1カ月定期をベースに算出され、企業によっては6カ月定期を6等分した金額で支給されることもあります。
支給対象となるのは「通勤に必要な区間」に限られます。
自動車・バイクで通勤する場合
公共交通機関を利用せず、車やバイクでの通勤が認められている場合には、ガソリン代相当として支給されるケースが多く見られます。
この場合、通勤距離(片道の距離)に応じて定められた金額が支給されることが一般的です。
たとえば、「片道10kmで月額4,200円支給」といった形で、社内規程に基づいて算出されます。
なお、車通勤が許可されるには、
- 就業規則に定めがあること
- 任意保険への加入
- 駐車場の自己負担有無
など、企業ごとの条件が設けられている場合もあるため、事前確認が必要です。
通勤手当には非課税限度額がある
通勤手当は給与の一部として支給されますが、一定の範囲内であれば所得税や住民税が課税されない「非課税扱い」となります。
この上限を超えると、超過分は課税対象となるため注意が必要です。
公共交通機関を利用する場合
電車やバスなどの公共交通機関で通勤している場合、月額15万円までの通勤手当は非課税となります。
多くの方にとって十分な金額ですが、遠距離通勤の場合などでこれを超えると、超過分は課税対象となります。
自動車・バイクで通勤する場合
自家用車やバイクを使って通勤する場合には、通勤距離に応じた非課税限度額が細かく定められています。
1ヶ月当たりの非課税限度額は以下の通りです。
距離が長くなるほど限度額も高くなります。ただし、会社がこの非課税枠を超える金額を支給する場合、その超過分は課税対象となります。
非課税の範囲内であっても、通勤手当は社会保険料の計算に含まれるため、給与全体に与える影響についても把握しておくことが重要です。
通勤手当は社会保険料の計算対象
通勤手当は給与の一部として扱われるため、社会保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」に含まれます。
つまり、通勤手当が支給されることで、その合計額に応じて健康保険料や厚生年金保険料の負担額が決まります。
このため、通勤手当が多い場合は社会保険料が増加する可能性があることを理解しておくことが重要です。
ただし、通勤手当の非課税範囲内であっても、社会保険料の計算対象になる点は異なりますので、税金との扱いの違いにも注意が必要です。
まとめ:通勤手当は転職時にしっかり確認すべき重要ポイント
通勤手当は転職先を選ぶ際に見落としがちなポイントですが、働き方や家計に大きく影響します。
支給の有無や条件は企業によって異なるため、事前にしっかり確認することが大切です。
もし不明点や疑問があれば、キャリアアドバイザーに相談するのもおすすめです。
通勤手当の仕組みを理解して、安心して転職活動を進めましょう。
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
転職コラムのおすすめ記事
-
2024/06/18
面接の心得!成功のための基本ポイントを解説
-
2024/08/10
転職で人材紹介をつかうメリットとは?具体的な利用方法を解説!
-
2024/06/25
履歴書の書き方を解説!就活・転職で成功するための具体的な手順とポイント
-
2024/07/04
面接での自己紹介、成功するための完全ガイド!具体例あり