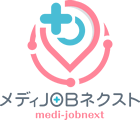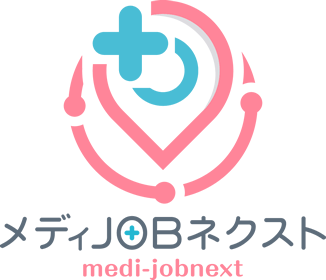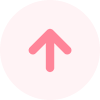2025/08/22
もしものケガや病気に備えて知っておきたい労災保険の基礎知識
仕事中や通勤中にケガをしたら、どうすればいいかご存じですか?
実は、そんな「もしも」のときに備えて、働く人を守る労災保険という制度があります。
正社員だけでなく、アルバイトやパートの方も対象になる心強い仕組み。
このコラムでは、労災保険の基本や補償内容、申請の流れまでをわかりやすくご紹介します。
労災保険とは?
労災保険が使える主なケース
労災保険で受けられる補償とは?
労災申請の流れ
まとめ:安心して働くために知っておこう
労災保険とは?
労災保険(正式には「労働者災害補償保険」)とは、仕事中や通勤中にケガをしたり、病気になったりした労働者に対して、治療費や休業中の補償などを行う国の保険制度です。
この保険は、すべての会社に対して加入が義務付けられており、正社員はもちろん、アルバイトやパートタイマー、契約社員も対象になります。
つまり、雇われて働いている人であれば、原則として誰でも自動的に労災保険の対象になるのです。
保険料は全額、事業主(会社)が負担しており、労働者が自分で申請したり、保険料を支払ったりする必要はありません。
知らないうちに守られている「働く人のためのセーフティネット」と言えるでしょう。
普段は意識することの少ない制度かもしれませんが、もしものときに生活を支えてくれる大切な存在です。
労災保険が使える主なケース
労災保険は、実際にどんなケースで使えるのでしょうか?
以下に主な例を紹介します。
業務中のケガ・事故
仕事中に起きたケガは、代表的な労災の対象です。たとえば、工場で機械に手を挟まれた、飲食店で転倒した、重い荷物を持ち上げて腰を痛めたなどが該当します。
通勤途中の事故
自宅と職場の往復中に起きたケガや事故も労災の対象になります。たとえば、通勤中に交通事故に遭った、駅の階段で転んでケガをしたなどのケースです。
※ただし、途中で私用の買い物などをしていた場合は対象外になることもあるので注意が必要です。
長時間労働による病気やメンタル不調
最近では、過重労働や強いストレスによる心身の不調も労災として認められるようになってきました。
たとえば、うつ病や過労による脳・心疾患(脳出血、心筋梗塞など)も、業務との関連が認められれば労災とされます。
職業病(仕事が原因でかかる病気)
アスベストによる肺疾患や、粉じんを吸い続けたことで起きる呼吸器疾患、化学物質による皮膚炎など、仕事環境が原因で発症した病気も労災の対象です。
労災保険で受けられる補償とは?
労災保険は、仕事中や通勤中にケガや病気をしたときに、治療費だけでなく、その後の生活を支えるためのさまざまな補償をしてくれます。
制度を知っておくことで、もしものときに安心して行動できるようになります。
主な補償内容を紹介します。
療養(治療)にかかる費用の補償(療養補償給付)
病院での診察・治療・入院・手術など、医療にかかる費用は原則すべて労災保険が負担します。健康保険のように自己負担(3割など)はなく、無料で治療を受けることができます。
※ただし、「労災指定医療機関」での受診が基本です。
休業中の給付(休業補償給付)
ケガや病気で働けなくなった場合、休業4日目から、給与のおおよそ8割が支給されます。
会社を休んでいる間も、生活に困らないよう配慮された制度です。
障害が残った場合の補償(障害補償給付)
治療を終えても、体に後遺障害が残ってしまった場合には、その等級に応じた一時金または年金が支給されます。
介護が必要になった場合の補償(介護補償給付)
労災が原因で重い障害が残り、介護が必要になった場合に支給されます。
常時または随時の介護が必要と認められると、月額の介護費用が支給されます。
万が一、死亡した場合の補償(遺族補償給付)
労災事故や病気で亡くなった場合、遺族には年金や一時金が支給され、葬祭料も支給されます。残された家族の生活を守るための補償です。
これらの補償は、健康保険ではカバーしきれない「仕事が原因のケガや病気」への特別な支援です。
労災申請の流れ
「これは労災かも?」と思ったとき、まず気になるのは「どうやって申請するのか」ということですよね。
ここでは、一般的な流れをステップごとに紹介します。
① ケガや病気が発生したら、すぐに会社に報告
まずは、上司や人事担当者などに状況を報告しましょう。できるだけ早く、できれば当日中に伝えることが大切です。
② 医療機関を受診(できれば労災指定病院へ)
治療を受ける際は、「労災指定医療機関」がおすすめです。ここで診察を受けると、治療費は労災保険から直接支払われるため、窓口での支払いが不要です。
(※指定病院以外でも受診できますが、一時的に立替が必要になる場合があります)
③ 労災申請書類を記入・提出
必要な書類を会社からもらい、記入して提出します。代表的な書類には以下のようなものがあります。
- 療養補償給付たる療養の給付請求書
- 休業補償給付支給請求書 など
通常は会社が作成・提出を手伝ってくれるケースが多いですが、場合によっては労働者本人が直接、労働基準監督署に申請することも可能です。
④ 労働基準監督署での審査
提出された申請書は、労働基準監督署が内容を確認・審査します。業務との関連性が認められれば、労災として認定され、補償が始まります。
⑤ 給付の開始
認定されると、治療費の支払い免除、休業補償給付の振込、その他の給付などが順次行われます。
まとめ:安心して働くために知っておこう
私たちが働く現場には、どんなに気をつけていても、思わぬケガや病気のリスクがつきものです。
だからこそ、「もしものとき」に自分を守ってくれる制度=労災保険の存在を知っておくことが大切です。
労災保険は、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員など、**立場に関係なく多くの労働者を対象にした“公的な安心”**です。
制度を知っていること自体が“自分を守る力”になります。
安心して働き続けるために、制度のことを知っておきましょう。
【参考文献】
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
転職コラムのおすすめ記事
-
2024/06/18
面接の心得!成功のための基本ポイントを解説
-
2024/08/10
転職で人材紹介をつかうメリットとは?具体的な利用方法を解説!
-
2024/06/25
履歴書の書き方を解説!就活・転職で成功するための具体的な手順とポイント
-
2024/07/04
面接での自己紹介、成功するための完全ガイド!具体例あり