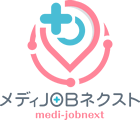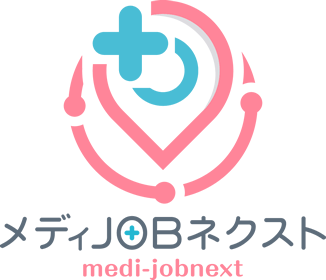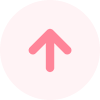2025/03/25
【管理栄養士必見】栄養指導を継続させるために必要な10個のポイント
管理栄養士が栄養指導を行うとき、患者さんが長く継続できる指導をすることが非常に重要です。
どんなに正しい栄養指導を行っても、続けなければ効果は期待できません。
そこでこの記事では、患者さんに栄養指導を継続してもらうために重要なポイント10個をご紹介します。
①検査値・身体計測と食事の関連を説明
②栄養素ではなく、食べ物・料理で説明
③計算・計量よりは留意点を指摘
④可能なことから実践
⑤意思の強さの確認と継続指導
⑥ツライ・難しい・面倒のイメージを持たせない
⑦期限付き我慢
⑧指導者自身も完璧でないことを自覚
⑨食事療法の宣言か問題点の飲食行動を記録
⑩叱るより褒める
①検査値・身体計測と食事の関連を説明
食事療法を患者さんに継続して実践してもらうためには、まず、検査値や体重が食習慣と密接に関連していることを理解してもらうことが大切です。
食生活の改善が必要だと伝えても、その重要性を十分に理解していないと、継続する意欲には繋がりません。
どの検査値が高いのか、その値が上がる原因は何か、そしてそれに関わる食習慣についてしっかりと説明し、患者さんに納得してもらうことが重要です。
こうした理解を深めてもらうことで、実行に移しやすくなり、改善への一歩を踏み出しやすくなることが多いです。
②栄養素ではなく、食べ物・料理で説明
患者さんと話す際には、栄養素ではなく、食べ物や料理を使って説明するよう心がけましょう。
管理栄養士はつい「タンパク質が…」と説明しがちですが、タンパク質などは専門用語であり、一般の方には分かりにくいことがあります。
そのため、肉や魚、料理名など、誰もが使う言葉で説明することが大切です。
ただし、腎臓病の患者さんの場合、肉や魚という言葉では説明が難しいこともあります。このような場合には、栄養素と食品・料理を併せて説明する必要があります。
③計算・計量よりは留意点を指摘
栄養指導では、患者さんが計算や計量をしなくても済む方法を提案することが、継続を促すうえで効果的です。
計算や計量が必要になると、食事療法が難しく感じられ、続ける意欲が低くなってしまいます。
そのため、分量を示す際には、「トマト1個」「お浸しが片手1杯」「サラダが両手1杯」など、簡単に判断できる方法で伝えることが重要です。
ただし、計量してきっちりと管理したい方には、計量方法を伝えることも有効です。
「食事療法は難しくない、むしろ簡単だ」と感じてもらうことが、継続のためには欠かせません。
④可能なことから実践
栄養指導で提案した内容を患者さんが実行できていなくても、決して責めるべきではありません。最初はできることから始めることが大切です。
複数の問題点がある場合には「どれから始められますか?」と尋ねてみましょう。患者さんが自分に合ったステップから取り組めるようサポートすることが重要です。
最初に1つできるようになったら、少しずつ増やしていき積み重ねていきます。
少しづつでも、長期的に見ると、確実に改善していきます。
⑤意思の強さの確認と継続指導
栄養指導の効果は、患者さんの意志の強さにも大きく影響されます。
改善の意志が強い患者さんであれば、2ヶ月に1回の頻度でも食生活を改善できる可能性があります。
しかし、意志が弱い場合は、1ヶ月に1回など、継続的にサポートすることが必要です。
強い意志がないと、リバウンドが起こりやすくなるため、患者さんの意志の強さを見極め、適切な指導頻度やアプローチを調整することが重要です。
⑥ツライ・難しい・面倒のイメージを持たせない
栄養指導では、「辛い・難しい・面倒」というイメージを与えないことが非常に大切です。
食事は日々のことなので、少しでもネガティブな印象を持たれると、取り組んでもらえなくなります。
例えばダイエットの場合、「制限」という言葉は極力避けるようにしましょう。
多くの人は、ダイエット中は空腹を我慢しなければならないと考えがちですが、それでは実践と継続には繋がりにくいです。
まずは、野菜や海藻など低エネルギーの食品でお腹を満たす方法を伝えましょう。
その上で、「お菓子は昼間に1回、饅頭なら1個程度であれば大丈夫そうですか?」と提案します。
「我慢」という言葉は使わず、ポジティブなアプローチで進めることがポイントです。
⑦期限付き我慢
患者さんの検査値や状態によっては、我慢が必要な場合もあります。
そんなときは、期限を決めて守ってもらうよう提案することが効果的です。
例えば、「アルコールは1ヶ月だけ禁止、その後は飲めるようになるから!」といった形で提案します。
このように一時的な制限を設けることで、1ヶ月間我慢できれば、検査値が改善し、2ヶ月目以降に再びお酒を飲んだ場合でも、数値が悪化することを避けたくなり、自然と量を減らす傾向があります。
「ずっとではなく、1ヶ月だけなら頑張れそう」と思ってもらいやすく、期限付きの提案は患者さんが取り組みやすくなる方法です。
⑧指導者自身も完璧でないことを自覚
栄養指導を行う上で、患者さんの気持ちに共感することは非常に大切です。
管理栄養士自身も完璧ではないことを自覚しておきましょう。
食べ過ぎてしまう気持ちや辛さを理解できることが、患者さんとの信頼関係を築くためには必要です。
その気持ちを忘れて、正しいことだけ伝えるのでは、患者さんはなかなか耳を傾けてくれません。
例えば、「週1回はお酒を飲んでも大丈夫」「昼間に食べるならお菓子を楽しんでもいいが、夕食後は控えましょう」など、実践的で柔軟な提案を行いましょう。
教科書通りの完璧な指導は理想的ですが、それだけでは継続的な実践には繋がりにくいことも多いです。
柔軟なアプローチを心がけることが重要です。
⑨食事療法の宣言か問題点の飲食行動を記録
食事療法を継続するために、「○○を控えている」といった内容を他の人に宣言することを勧めるのも効果的な方法です。
人に伝えることで、言ったからには守らなければならないという意識が高まり、実行に繋がることが多いです。
また、全ての食事記録をつけるのは面倒に感じることが多いですが、問題となっている部分だけに絞って記録することは、意外と多くの人ができるものです。
例えば、以下のような項目を記録してもらうことが有効です。
・お酒の量
・お菓子の種類や量
・清涼飲料水の種類や量
・食べた時間
・野菜の摂取量
・肉や魚の料理の種類と量
患者さんの食生活で特に問題となっている習慣を1つ選んで記録してもらいましょう。
記録することで、自分が思っていた以上に多く摂取していたことに気づき、反省や改善のきっかけになります。
⑩叱るより褒める
継続的な栄養指導を行うためには、「叱る」よりも「褒める」ことを実践することが大切です。
指導内容を守れず、前回よりも体重が増えてしまった場合でも、「太っちゃだめじゃない!」と怒るのではなく、「1kg増えただけで良かったね」と、寄り添う言葉をかけてあげましょう。
こうすることで、患者さんは「次はもっと真剣に取り組んでみよう」と前向きな気持ちになりやすくなります。
栄養指導を受ける患者さんの多くは、管理栄養士よりも年齢が高く、社会的地位や人生経験を積んでいる方々です。
そのため、自分より若い栄養士に叱られることは不愉快に感じ、指導を続ける意欲を失ってしまう可能性があります。
もし前回と比べて少しでも改善できたことがあれば、どんな小さなことでも見つけて褒めてあげることが重要です。
こうした励ましを通じて患者さんのやる気を引き出し、健康への意識を持続させることも、管理栄養士の大切な役割の一つです。
***
以上、患者さんが継続できる栄養指導のための重要なポイント10個をご紹介しました。
これらを日々の栄養指導に取り入れ、患者さんがより良い食習慣を身につけられるようサポートしていきましょう。
【参考文献】
- 足立香代子(2012年)『検査値に基づいた栄養指導』第2版第3刷、株式会社チーム医療
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年、管理職6年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
栄養士コラムのおすすめ記事
-
2024/06/18
管理栄養士の大変なこととは?〜ストレスや負担を軽減する方法も紹介〜
-
2024/06/18
管理栄養士の仕事内容とは?職場別に詳しく解説!
-
2024/06/18
管理栄養士による栄養指導とは?病院での実践経験から得た知見
-
2024/07/04
成功する管理栄養士になるための必須スキル10選