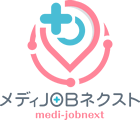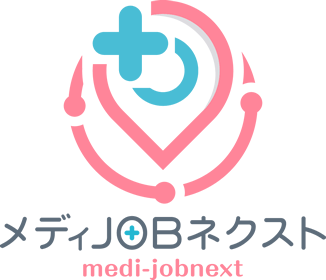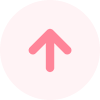2025/02/05
日本人の食事摂取基準(2025年版)の変更点を分かりやすく解説
日本人の食事摂取基準(2025年版)が厚生労働省より公表されました。
これを受け、2020年版からの変更点・特徴について、要点を絞って解説します。
・骨粗鬆症とエネルギー・栄養素との関連についての新たな解説
・食物繊維の測定法変更に関する注意
・鉄の耐容上限量が削除
骨粗鬆症とエネルギー・栄養素との関連
2025年版では、骨粗鬆症とエネルギー・栄養素の関係についての項目が新たに加えられました。
日本人の食事摂取基準は、「Ⅰ総論」と「Ⅱ各論」の2つのセクションに分かれています。その「Ⅱ各論」の中に、「3 生活習慣病及び生活期の維持・向上に係る疾患等とエネルギー・栄養素との関連」という項目があります。
この項目では、疾患とエネルギー・栄養素の関連について説明されていますが、今回新たに「骨粗鬆症」が加わりました。
▼以下の項目になりました。
(1)高血圧
(2)脂質異常症
(3)糖尿病
(4)慢性腎臓病(CKD)
(5)骨粗鬆症 ←NEW!!!
骨粗鬆症の最終目標は「骨折予防」とし、食事との関連が解説されています。
▼特に関連の深いエネルギー・栄養素は以下の4つが挙げられています。
・ビタミンD
・たんぱく質
・エネルギー(体格)
カルシウム
カルシウムについての内容をまとめると以下の通り。
・十分なカルシウム摂取は骨量を維持するために必要。
・カルシウム摂取が不足すると、低骨量のリスクが高くなる。
・しかし、中高年においてカルシウム摂取量を増やしても、骨密度低下や骨折予防効果はあまり大きくない。
・サプリメントを使った研究が多いが、1,000mg/日以上のカルシウムサプリメント摂取は心筋梗塞のリスクを高める可能性がある。
・1,000mg/日以上のカルシウムサプリメント使用には慎重であるべき。
ビタミンD
ビタミンDについての内容をまとめると以下の通り。
・血中25-ヒドロキシビタミンD濃度(食事・紫外線照射のVDを反映)を20 ng/mL以上に保つことは、骨粗鬆症予防に重要。
・しかし、ビタミンDサプリメントの効果については、今後の検証が必要。
・ビタミンDを維持するためには、食事からの摂取と適切な日光曝露が推奨される。
たんぱく質
たんぱく質についての内容をまとめると以下の通り。
・骨形成にたんぱく質の摂取不足を避けることは重要。
・しかし、現時点では骨粗鬆症予防におけるたんぱく質摂取の影響について、明確な結論は出ていない。
エネルギー(体格)
エネルギー(体格)についての内容をまとめると以下の通り。
・骨粗鬆症予防や骨折リスク低減のためには、低体重は避けるべき。
・BMIが25 kg/m²以上の場合、骨折リスクは部位や性別によって異なるが、おおむね低いと考えられる。
・しかし、高血圧や糖尿病、心筋梗塞、脂質異常症などのリスクが高まるため、過体重・肥満は推奨できない。
この4つの他に、ビタミンC・ビタミンKも骨の健康に関与しているものの、現在のところ、それらの摂取が骨粗鬆症予防に直接的な効果をもたらすかどうかは、はっきりしないということが示されていました。
食物繊維含有量の測定法の違いに注意
食物繊維の目標量と、実際の栄養計算で求めた食物繊維摂取量を比較する際は、注意が必要ということが喚起されています。
食物繊維は、日本食品標準成分表が七訂から八訂に変わった際に、測定方法が一部変更になりました。
▼食物繊維の測定方法
八訂:AOAC.2011.25法(※)
※一部の食品では引き続きプロスキー変法が使用されています
この変更により、八訂で測定された食物繊維量は、七訂に比べて高く算出されることが多くなります。
AOAC.2011.25法では、従来のプロスキー変法に比べ、食物繊維として測定される物質が増えているため、今までの測定方法よりも、食物繊維量が多く算出されるからです。
▼実際に、日本食品標準成分表が七訂から八訂に変わった際に食物繊維量が大きく変化した食品の例(一部のみ)を表にしました。
このように、七訂から八訂に変わった際に食物繊維量が大きく変化しているのが分かります。
しかし、今回の日本人の食事摂取基準2025年版で設定された食物繊維の目標量は、七訂相当の測定法を用いて算出しています。(目標量を定める根拠となる研究が、七訂相当の食物繊維測定法が用いられているため)
そのため、八訂を用いて栄養計算した食物繊維量の評価を行う場合、この目標量を摂取できていたとしても、生活習慣病予防の観点からは不十分である可能性があります。
このような背景を理解した上で、食物繊維の摂取量を評価する必要があります。
そのため、日本食品標準成分表(八訂)を用いた栄養計算を行い、その適切性の評価を行う場合、成人においては目指すべき食物繊維摂取量である 25 g/日を目安とするのも1つの方法、と書かれていました。
鉄の耐容上限量が削除された
日本人の食事摂取基準2020年版では鉄の耐容上限量が設定されていましたが、2025年版ではこれが削除されました。
その理由は、遺伝子の異常やアルコール性肝障害がない場合、食事からの鉄の過剰摂取が胃腸症状を除いて他の健康障害を引き起こす明確な証拠が見当たらないためです。
そのため、男女ともに1歳以上で設定されていた鉄の耐容上限量はすべて無しになりました。
***
以上が、日本人の食事摂取基準2025年版での大きな変更点・特徴でした。
詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年、管理職6年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
最新業界情報のおすすめ記事
-
2024/06/20
管理栄養士が知っておきたい令和6年診療報酬改定の内容
-
2025/07/08
マイナンバーカードと免許証の一体化のメリット・デメリットとは?
-
2024/08/09
栄養ケアステーションとは?サービス内容と利用方法を解説
-
2024/12/25
健康日本21(第三次)分かりやすく解説!管理栄養士が知っておきたい項目