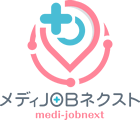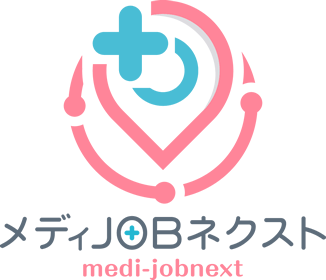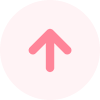2025/05/12
米の価格高騰の理由と私たちへの影響
日本人の主食として欠かせないお米ですが、その価格が大きく上昇し、家計に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
同じ品種・同じ量のお米でも、以前と比べて価格がほぼ2倍に跳ね上がっているケースも見られます。
この米価の高騰には、単一の原因ではなく、いくつもの複雑な要因が絡み合っています。
本記事では、米価上昇の背景と、それが私たちの暮らしに与える影響についてわかりやすく解説していきます。
米の価格は今までの約2倍にまで高騰
米の価格が全国的に上昇し始めたのは、2024年の夏以降のことです。
そして2025年3月には、5kgあたり約4,000円と、前年の約2,000円からほぼ1.9倍にまで高騰しました。この水準は1990年以降で最も高く、かつてない値上がりです。
主食として日常的に消費されるお米の価格上昇は、家計に直接影響を及ぼし、消費行動にも大きな変化をもたらしています。
米の価格が高騰している4つの原因
米の価格が高騰している原因は以下の4つがあります。
①異常気象と収穫量の減少
②生産コストの上昇
③業者間の競争激化
④需要の増加
①異常気象と収穫量の減少
お米の価格が高騰した原因の1つは、異常気象による収穫量の減少によるものです。
2023年の夏、記録的な猛暑となり、全国的に高温障害や水不足が発生しました。 これにより、米の成長が妨げられ、収穫量が減少しました。
特に高温障害によって米が十分に成長しないケースが多発し、供給不足を引き起こしました。
②生産コストの上昇
生産コストの上昇も、米の価格高騰に影響しています。肥料や燃料の価格が高騰し生産コストが増加しました。
特に肥料の価格は世界的な影響を受けて高騰しており、農家の負担が増しています。
③業者間の競争激化
お米の価格高騰の一因として、米の確保をめぐる業者間の競争が激しくなっていることが挙げられます。
この影響で、仕入れ価格も上昇傾向にあります。
④需要の増加
お米の需要が増加したことも、価格高騰の一因となっています。
コロナ禍の収束に伴い、日本を訪れる外国人観光客が増加し、それに伴ってお米の消費量も伸びました。
特に、外食産業やホテル業界では米の使用量が増え、全体的な需要の押し上げにつながっています。
管理栄養士の現場から見る“米高騰”
米の価格高騰は、一般家庭だけでなく、医療・福祉・保育などの「食事提供の現場」にも深刻な影響を与えています。
特に病院や介護施設など、1日3食を提供する施設では、ご飯が主食として頻繁に登場し、1日2~3回の提供が一般的です。
そのため、米は食材費全体の中で占める割合が高くなりやすいのです。
施設で働く管理栄養士にとって、食材費の管理は非常に重要な業務であり、米価高騰は現場にとって大きな打撃となっています。
「栄養バランスを保ちながら、限られた予算内でどう対応するか」というジレンマに直面し、多くの管理栄養士が日々工夫を重ねています。
中には、食材の使い回しや調理方法の見直し、メニューの変更を余儀なくされている施設もあることでしょう。
米の高騰はしばらく続くと予測されていますが、私たちにできることは、米以外の食材を工夫してコスト削減を図ることに加え、1粒のお米も無駄にせず大切に食べることです。
管理栄養士として、米が持つ栄養価や文化的な重要性を改めて伝えることも欠かせません。
今一度、主食としての米の重要性を再認識し、残食を減らし、食材を無駄にしないための工夫をしていきたいです。
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年、管理職6年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
最新業界情報のおすすめ記事
-
2024/06/20
管理栄養士が知っておきたい令和6年診療報酬改定の内容
-
2025/07/08
マイナンバーカードと免許証の一体化のメリット・デメリットとは?
-
2024/08/09
栄養ケアステーションとは?サービス内容と利用方法を解説
-
2024/12/25
健康日本21(第三次)分かりやすく解説!管理栄養士が知っておきたい項目