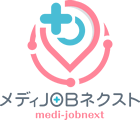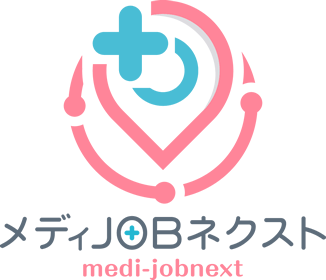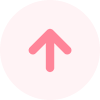2024/07/16
日本の食料自給率とは?現状と課題、未来への提案。
私たちの食卓に並ぶ食材のうち、どれだけが国内産でしょうか?
日々の食事を楽しむ私たちの裏側には、日本の食料自給率の問題が潜んでいます。
近年、日本の食料自給率は低下の一途をたどっており、私たちの食生活にも影響を及ぼしています。
輸入食材に依存する現状は、価格変動や食の安全性に対する懸念を引き起こします。
この記事では、日本の食料自給率の現状と課題について詳しく探り、未来に向けてどのように対策を講じるべきか考えてみましょう。
私たち一人一人ができることは何か、一緒に考えていきましょう。
▷▷目次
1. 現状の食料自給率は何%?
2. 食料自給率が低いとどんな影響があるの?
3. 日本の食料自給率への取り組みは?
4. 私たちにできることは何だろう?
5. まとめ
現状の食料自給率は何%?
日本の食料自給率は年々低下しており、令和4年のデータによると、カロリーベースでの自給率は約38%です*1。
これは、私たちが消費する食料の約60%以上を海外から輸入していることを意味します。
主要な先進国と比較しても、非常に低い水準です。
例えば、アメリカやフランスは100%を超える自給率を誇り、国内での食料生産を重視しています*2。
日本の自給率低下の原因は、食生活の多様化が進んだことが原因です。
高齢化による農業従事者の減少や、農地の減少なども今後の食料自給率に大きく影響しています*3。
これから、私たちがどのように食料自給率を改善していくべきかを考える必要があります。
食料自給率が低いとどんな影響があるの?
日本の食糧自給率が低いことは、さまざまな影響をもたらします。
まず、経済的影響として、輸入食材に依存することで国際市場の価格変動に敏感になり、食品価格が急騰するリスクがあります。
また、輸送コストや関税もかかるため、消費者の負担が増加します。
次に、食の安全性に対する懸念があります。
輸入食材の生産過程や品質管理が国内基準と異なるため、健康へのリスクが高まる可能性があります。
さらに、環境への影響も無視できません。
輸送による二酸化炭素の排出が増え、地球温暖化を助長します。
国内農業の衰退も問題です。
農業が縮小すると農村地域の活力が失われ、食料供給の安定性が脅かされます。
このように、食糧自給率の低下は私たちの生活全般に深刻な影響を及ぼします。
日本の食料自給率への取り組みは?
では、日本はこの食料自給率に対してどんな取り組みをしているでしょうか?
以下の取り組みを重点的に推進しています。*4
食料消費に関しては、消費者と食・農のつながりを深めるため、食育や国産農産物の消費拡大、地産地消、和食文化の保護・継承、食品ロス削減などの施策を推進しています。
農業生産においては、需要の変化に対応した生産・供給体制を整え、高付加価値化や生産コストの削減、輸出拡大を目指しています。
地域の生産者と消費者の交流を促進し、持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成、農地の集積、スマート農業の導入、生産性の向上を図っています。
また、耕作放棄地の有効活用や適切な維持管理を推進し、地域農業の活性化を目指しています。
私たちにできることは何だろう?
では、私たち一人ひとりができることは何があるでしょうか?
まず、家庭でできることとして、家庭菜園を始めたり、地元の農産物を積極的に購入したりすることで、地産地消を推進できます。
次に、企業ができる取り組みとして、CSR活動や持続可能なサプライチェーンの構築があります。地元農家と連携し、国産食材の使用を増やすことが求められます。
最後に、教育と啓発の分野では、学校教育や地域での食育活動を推進し、子供たちに食と農の大切さを教えることが重要です。
これらの取り組みを通じて、私たち全員が食糧自給率の向上に貢献できます。
まとめ
日本の食糧自給率は約38%と低く、輸入食材に依存しています。
これにより、価格変動や食の安全性、環境負荷など多くの問題が生じています。
政府は食育や地産地消、農業技術革新などの取り組みを推進しています。
私たちも家庭菜園や地元産品の購入、企業のCSR活動、教育と啓発を通じて、食糧自給率の向上に貢献できます。
一人ひとりの行動が未来の食の安全と安定につながります。
今回の記事を通して、日本の食料自給率について考えるきっかけとなれば嬉しいです。
また、以前「輸入食品について」のセミナーにも参加しました。
↓興味のある方は、この機会にぜひレポート記事もご覧ください。
セミナーレポート「知りたい!輸入食品~輸入食品の安全性確保について~」
参考文献
*4. 1 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた取組:農林水産省
筆者のプロフィール
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の正社員勤務11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年、管理職6年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさまのお役に立てる様な情報発信を行っていきます。
最新業界情報のおすすめ記事
-
2024/06/20
管理栄養士が知っておきたい令和6年診療報酬改定の内容
-
2025/07/08
マイナンバーカードと免許証の一体化のメリット・デメリットとは?
-
2024/08/09
栄養ケアステーションとは?サービス内容と利用方法を解説
-
2024/12/25
健康日本21(第三次)分かりやすく解説!管理栄養士が知っておきたい項目