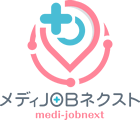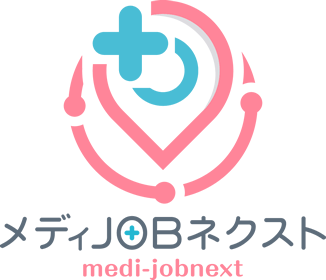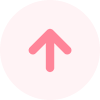2025/04/22
2025年4月から育休制度が変わる!改正ポイントをわかりやすく解説
2025年4月から、育児休業給付に関する新たな制度が創設されました。
また同時に、「育児・介護休業法」も改正され、育児期における柔軟な働き方を支援する内容が拡充されました。
これらにより、子育てと仕事の両立がよりしやすくなり、子育て世代にとって働きやすい環境が整備されています。
本記事では、育児休業給付や今回の法改正によって導入された子育てに関する新しい仕組みや変更点を、わかりやすく解説します。
・子の看護休暇の見直し
・残業免除の対象拡大
・時短勤務の代替措置にテレワーク追加
・育児のためのテレワーク導入
・育児休業の取得状況の公表義務の適用拡大
・育児期の柔軟な働き方の措置(2025年10月~)
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(2025年10月~)
「まだ内容をチェックしていない」という方はぜひ、この機会に最後までご覧ください。
出生後休業支援給付金の【新設】
2025年4月から新たに「出生後休業支援給付金」制度が創設されました。
出生後休業支援給付金は、子どもが生まれた直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が働いていない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取った場合に、最大28日間支給される給付金のことです。
この制度の新設により、両親ともに、他制度と併せると、28日間の給付金が手取りの10割相当になります。
詳しい制度内容、給付条件などは▼こちらをご確認ください。
育児時短就業給付金の【新設】
2025年4月から新たに「育児時短就業給付金」制度が創設されました。
育児時短就業給付金は、2歳未満の子どもを育てるために時短勤務をした人が、時短になったことで給料が減った場合に支給される給付金のことです。時短前の給料の10%相当額が支給されます。
この制度の新設により、時短勤務制度を選択しやすくすることを目的とされています。
詳しい制度内容、給付条件などは▼こちらをご確認ください。
子の看護休暇の見直し
2025年4月から「子の看護休暇の見直し」が行われました。
変更内容は以下の通りです。
この変更により、看護休暇の対象が小学3年生にまで拡大され、行事参加等でも取得できるようになりました。また、入社6ヶ月に満たなくても、条件を満たすことで看護休暇が使用できます。
詳しい制度内容、条件などは▼こちらをご確認ください。
残業免除の対象拡大
2025年4月から、所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されました。
これまでは3歳未満の子どもを育てている場合に限り、残業が免除されていましたが、今回の改正により、対象が小学校就学前の子どもに引き上げられました。
これにより、より長い期間にわたって、子育てと仕事の両立がしやすくなりました。
詳しい制度内容、条件などは▼こちらをご確認ください。
時短勤務の代替措置にテレワーク追加
2025年4月から、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置として、テレワークが新たに追加されました。
これまでは、時短勤務が難しい業務の場合、以下の①②の代替措置が提供されていましたが、③テレワークも加わりました。
②始業時刻の変更等
③テレワーク(新設)
これにより、3歳未満の子どもを育てる親にとって、子育てと仕事を両立させやすくなる選択肢が広がりました。
詳しい制度内容、条件などは▼こちらをご確認ください。
育児のためのテレワーク導入
2025年4月から、3歳未満の子どもを育てている従業員がテレワークを選べるよう、事業主に措置を講じることが努力義務化されました。
これにより、子育てと仕事を両立させやすくするための選択肢として、テレワークが利用しやすくなります。
詳しい制度内容、条件などは▼こちらをご確認ください。
育児休業の取得状況の公表義務の適用拡大
2025年4月から、育児休業取得状況の公開義務の対象企業が拡大されました。
これまでは、公開義務の対象となる企業は従業員数1000人超の企業でしたが、今後は従業員数300人超の企業にも適用されます。
これにより、育児休業取得の状況がより広く公開されることで、企業の育児支援制度の改善が進み、働く親の支援がさらに強化されることが期待できます。
詳しい制度内容、条件などは▼こちらをご確認ください。
育児期の柔軟な働き方の措置(2025年10月~)
2025年10月から、事業主は、3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者に対して、以下の5つの選択肢のうち、2つ以上の措置を実施することが求められるようになりました。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選んで利用することができます。
選べる措置は▼以下の通りです。
・テレワーク(月に10日以上の勤務)
・保育施設の設置・運営(ベビーシッター手配など)
・新たな休暇の付与(年に10日以上の休暇)
・短時間勤務制度(1日6時間勤務など)
これにより、3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者が、柔軟な働き方を選択できるようになり、子育てと仕事の両立がしやすくなることが期待できます。
詳しい制度内容、条件などは▼こちらをご確認ください。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(2025年10月~)
2025年10月から、事業主は、労働者が妊娠・出産の申し出をした時と、子どもが3歳になる1年前までの間に、子育てと仕事の両立について労働者の意向を聞き、それに配慮することが義務化されました。
聴取内容は▼以下の通り。
・勤務地(就業場所)
・両立支援制度の利用期間
・仕事と育児を両立するための就業条件(業務量や労働条件の調整)
これにより、子育て世代の希望や状況が職場に伝わりやすくなり、より働きやすい環境づくりが期待されます。
詳しい制度内容、条件などは▼こちらをご確認ください。
まとめ
この記事では、2025年4月から拡充された「育児休業給付」および、「育児・介護休業法」の子育て支援に関する主な改正ポイントをご紹介しました。
今回の改正によって、子育て世代がライフスタイルに合わせた働き方を選びやすくなり、仕事と育児の両立がよりしやすい環境が整備されています。
改正内容を正しく理解し、自分に合った支援制度を上手に活用することが、無理なく両立を進めるための第一歩です。
ご自身はもちろん、周りの子育て世代の方々のためにも、ぜひ制度の利用を前向きに検討してみてください。
詳しい内容は、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年、管理職6年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
最新業界情報のおすすめ記事
-
2024/06/20
管理栄養士が知っておきたい令和6年診療報酬改定の内容
-
2025/07/08
マイナンバーカードと免許証の一体化のメリット・デメリットとは?
-
2024/08/09
栄養ケアステーションとは?サービス内容と利用方法を解説
-
2024/12/25
健康日本21(第三次)分かりやすく解説!管理栄養士が知っておきたい項目