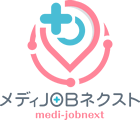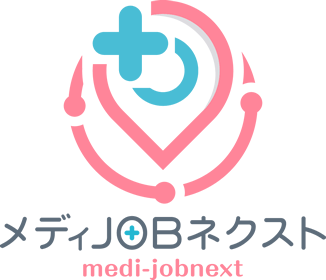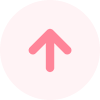2025/08/28
セミナーレポート「食品添加物~その役割と安全性~」
セミナー概要
令和7年8月27日(水)に開催された「食に関するセミナー」にオンラインで参加しました。
このセミナーは近畿農政局が主催するセミナーで、消費者を対象に食に関する正確で分かりやすい情報を提供することを目的として行われました。
プログラムは以下の通り。
--------------------------------------------------------------------
食品添加物について~その役割と安全性~
講師:一般社団法人 日本食品添加物協会 常務理事 川岸昇一 氏
--------------------------------------------------------------------
食品添加物について~その役割と安全性~
食品添加物とは、食品の製造・加工の過程で目的を持って使用される物質であり、食品衛生法に基づいて厳しく管理されています。
添加物として使用が許可されているのは、国が安全性と有用性を確認し、指定したもののみです。使用基準や成分規格が定められており、安全性が確保されたうえで流通しています。
食品添加物として指定されるための条件
添加物として指定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①安全性が実証または確認されるもの
②使用により消費者に利点を与えるもの
(例:食品の製造に必要不可欠、栄養価の維持、保存性の向上、外観や風味の改善など)
③すでに指定されている物と比較して、同等以上か別の効果を発揮するもの
④原則として科学分析などにより、その添加を確認しうるもの
食品添加物4つの役割
①食品の製造又は加工するときに必要
→豆腐の豆腐用凝固剤、中華麺のかんすい など
②食品の品質を保つ
→菌を抑制・保存効果の保存料、油の酸化を防ぐ酸化防止剤 など
③食品の嗜好性の向上
→色、味、香り、食感など五感にアピールする着色料、香料 など
④栄養価の補填・強化
→ビタミン、ミネラル、アミノ酸など
食品添加物の社会的な役割
食品添加物は、単に食品の見た目や味を整えるだけでなく、社会的な課題解決にも貢献しています。
・食品ロス削減への貢献
・食塩摂取への抑制への貢献
・災害など非常時において加工食品の役割
・新しい加工食品(メタボ対策や嚥下困難、咀嚼困難、介護食など)
安全性の考え方とリスク分析
食品の安全性は、以下の2つの視点で判断されます。
・経験的判断:長年の食経験に基づくもの
・科学的判断:科学的データに基づいてリスクを評価し、最小限に抑える考え方
食品添加物の安全性評価は「リスク分析」の枠組みに基づいており、次の3要素で構成されます。
①リスク評価(食品安全委員会):動物実験などにより最大無毒性量を決定し、それに基づいて一日摂取許容量(ADI)を設定
②リスク管理(消費者庁・厚労省・農水省):指定・使用基準の策定、摂取量調査などを実施。実際の摂取量はADIの0.1%程度と非常に少ないことが報告されている
③リスクコミュニケーション:関係者間および消費者との情報共有と対話を通じた理解促進
食品添加物のキーメッセージ
①有用性がなくては食品添加物でない
②使ってよい食品添加物は決められている
③安全性が科学的に確認されている
④食品添加物の品質が決められている
⑤摂取しても良い量が決められている
⑥実際に摂りすぎていないか確認されている
⑦食品添加物はその効果を達成するために必要な最小量で使用する
まとめ
・100%安全な食べ物はありません。食の安全はリスク分析の考え方により科学的に判断しましょう。
・食品添加物はリスク評価され、人の健康に影響を及ぼさないようにリスク管理されています。
・食品に関する人たちは自己の発言に責任を持ち、正しい情報発信に努め、消費者の不安感を利用するような食品開発は控えましょう。
・食費者は、食に関する知識と理解を深め、いたずらに不安がらず、楽しくバランスの良い食生活を心がけましょう。
セミナーを受けての感想
今回のセミナーを通して、食品添加物について改めて多くの気づきを得ることができました。たとえば、豆腐は食品添加物なしでは作れないという話は、身近な食品だけにとても印象的でした。また、食品添加物が食品ロスの削減や、食塩摂取量の抑制に貢献しているという視点は、これまであまり考えたことがなかったため、なるほどと納得しました。
私自身、管理栄養士として学んできたつもりではありましたが、「無添加」「オーガニック」といった表示を見ると、やはりそれらの方が良いのではないかと感じてしまうことがあります。最近はネットやSNSを通じて様々な情報があふれ、無添加=健康的というイメージが強く広まっていると感じます。
しかし今回の講義を通じて、食品添加物は単に「悪いもの」ではなく、適切に使用されることで私たちの食生活に多くのメリットをもたらしているということを、改めて認識しました。食品添加物は法律に基づいて科学的に評価・管理されており、安全性が確認されたうえで使用されています。そのため、「添加物が入っているからダメ」といった極端な見方をするのではなく、正しい知識に基づいて判断する姿勢が大切だと感じました。
管理栄養士として、今後は自分自身が食品添加物に関する正しい知識を持ち、ただ「無添加」を推奨するのではなく、その背景や意味も含めて、消費者に正確な情報を伝えていく責任があると感じました。今回のセミナーは、専門職としての立場を改めて考え直す良い機会となりました。
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
セミナー情報のおすすめ記事
-
2025/11/14
セミナー実施報告:「食品群別荷重平均成分表と食品構成表作成」
-
2024/09/20
セミナーレポート「 ランチ形式で学ぶ在宅での食支援~トリプル改定 医療・介護・在宅のポイント!~」
-
2024/09/24
セミナーレポート 「2024年度食物アレルギーセミナーin神戸 ~共に創ろう 笑顔あふれる 未来~」
-
2024/10/17
セミナーレポート「正しく知ろう!健康食品~健康食品を利用するにあたっての留意点などについて~」