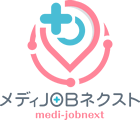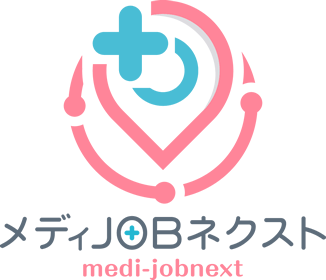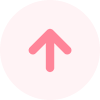2025/07/24
セミナーレポート「リスクコミュニケーションセミナー~食品のリスクを正しく理解し、健康被害を防ぐ~」
セミナー概要
令和7年7月23日(水)に開催された「リスクコミュニケーションセミナー~食品のリスクを正しく理解し、健康被害を防ぐ~」のセミナーにオンラインで参加しました。
このセミナーは、公益社団法人 日本栄養士会が主催するセミナーで、リスクコミュニケーションの一層の推進を目的に行われました。
プログラムは以下の通り。
--------------------------------------------------------------------
1.「食の安全・安心リスクコミュニケーション~食品安全行政の仕組みと消費者庁の取り組み~」
講師:市川翔太 氏(消費者庁消費者安全課)
2.「保健機能食品等について」
講師:古賀恵 氏(消費者庁食品表示課保険表示室食品表示調査官)
3.「いわゆる健康食品などの種類と正しい利用に向けて留意すべきこと」
講師:種村菜奈枝 氏(福島大学農学群食農学類食品化学コース准教授)
--------------------------------------------------------------------
1.「食の安全・安心リスクコミュニケーション~食品安全行政の仕組みと消費者庁の取り組み~」
日本の食品安全行政の枠組み:リスクアナリシス
・リスク評価・・・どのくらいなら食べても安全か評価
・リスク管理・・・食べても安全なようにルールを決めて、監視
・リスクコミュニケーション・・・リスク評価やリスク管理の全過程において、情報共有や意見交換を行うこと
関係府長官の役割分担
・消費者庁・・・食品衛生に関するリスク管理(規格・基準)
・厚生労働省・・・食品衛生に関するリスク管理(監視・指導)
・農林水産省・・・農林水産物などに関するリスク管理
消費者庁のリスクコミュニケーション
消費者庁は、消費者が正確な情報に基づいた消費行動を行うために情報提供を行っている。
取り組みは以下の通り。
・全国各地での意見交換会などの実施
・多様な主体によるリスクコミュニケーションの推進(イベントなど)
・正確な情報発信(資料配布・SNSなど)
情報収集のひとつとして以下のWebサイトをご活用ください。
2.「保健機能食品等について」
保健機能食品には以下の3種類がある
・栄養機能食品
・機能性表示食品
・特定保健用食品
栄養機能食品とは
特定の栄養成分の補給を目的として摂取するものに対し、その栄養成分の機能表示を行うもの。自己認証制で、定められた栄養量の範囲内であれば表示可能。
例:ビタミンCを摂りたい人に対し、「ビタミンCは皮膚や鼓膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素」という内容を商品に表示する
機能性表示食品とは
健康な人を対象に、健康の維持や増進が期待できることを表示できる食品です。国の審査はありません。
機能性表示食品制度の見直し
紅麹関連製品にかかる事案を受け、以下の見直しが行われました。
・医師の診断による健康被害情報の保健所などへの提供の要件化
・天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品についてGMP(適性製造規範)に基づく製造管理を要件化
・摂取上の注意事項の記載方法などの表示方法の見直し
特定保健用食品(トクホ)とは
特定の健康効果が期待できる食品のことです。消費者庁の許可が必要で、有効性や安全性の国の審査が必要です。
例: 本品は、~~が含まれているため、便通を改善します。おなかの調子を整えたい方やお通じの気になる方に適しています。
特別用途食品とは
乳児や妊産婦、授乳婦、嚥下困難者、病者などの健康の保持・回復を助ける食品のことです。消費者庁の許可を受けて、特別の用途を表示しています。
例:「経口補水液」感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態の際に、水・電解質の補給に適しています。
3.「いわゆる健康食品などの種類と正しい利用に向けて留意すべきこと」
いわゆる「健康食品」とは
医薬品以外の以下の食品をまとめていわゆる「健康食品」といいます。
・特定保健用食品
・栄養機能食品
・機能性表示食品
・その他のいわゆる「健康食品」
いわゆる「健康食品」の利用にあたる留意点
(1)粗悪品に注意
品質に問題がある商品もあるので注意が必要です。
過去に、以下のような事例がありました。
・ダイエット用ゼリーの中に医薬品成分が入っており健康被害
・リラックス効果クッキーに大麻成分が入っており健康被害
・紅麹の食中毒(青カビ)による健康被害
(2)利用の誤りに注意
商品自体には問題がなくても、利用方法を誤ると予期せぬ健康被害が発生する場合があります。
以下のような事例が過去にありました。
・ビタミンEサプリとイブプロフェンの併用でビタミンE中毒
・複数の食品からβカロテンの過剰摂取でクロレラ中毒
・チアミン・ナイアシンサプリメントからナイアシン過剰摂取
健康食品をとっていて体調に異変を感じたときの対応ステップ
ステップ1:体調の異変がいつからかを確認する
まず、「その体調の変化はいつから始まったか?」を考えます。
ステップ2-1:異変が健康食品の摂取前からある場合
健康食品を飲む前から体調が悪かったのであれば、健康食品は原因ではない可能性が高いです。
ステップ2-2:異変が健康食品の摂取後から始まった場合
健康食品を飲んだあとから体調が悪くなったのであれば、すぐにその健康食品の摂取をやめましょう。
ステップ3-1:中止しても体調が改善しない場合
健康食品をやめても体調が悪いままなら、速やかに医療機関を受診してください。
ステップ3-2:中止して体調が回復した場合
健康食品が原因の可能性があります。近くの薬局で薬剤師に相談しましょう。
ステップ4:相談・報告を行う
必要に応じて、保健所や健康食品の販売元に連絡しましょう。
セミナーを受けての感想
今回のセミナーを通して、健康食品に伴うリスクについて改めて考えさせられました。
まず、「健康食品」とひとくちに言っても種類が多く、名前も似ているため、区別や理解が難しいと再認識しました。これまで何度も学んできたにもかかわらず、管理栄養士である自分自身でさえ、説明を求められてもすぐには整理して話せないのが現状です。一般の方々にとっては、さらに分かりづらいだろうという印象を持ちました。
また、近年は、SNSなどを通じて健康食品に関する情報や広告を目にする機会が増えています。誤った情報に触れる機会も少なくありません。だからこそ、正しい知識を根拠をもって発信していくことの重要性を強く意識させられました。
実際に健康被害の事例を知り、健康食品の「リスク」という側面を軽視してはいけないと痛感しました。食品であっても、使用の仕方によっては健康を損なう可能性があるという現実を、もっと多くの人が理解する必要があります。
サプリメントは、手軽に摂取できるという利便性から広く利用されていますが、その「手軽さ」が落とし穴になることもあります。私自身、その便利さにひかれる気持ちがわかる一方で、基本となるのはあくまで「バランスのとれた食事」であるという考えを再確認しました。
今後は、健康食品に対する正しい情報提供に加えて、「まずは食事から」という基本の考え方を、多くの人に伝えていく責任を感じました。
株式会社メディカルフロンティア 専属ライター(管理栄養士)
▼管理栄養士の現場経験11年
▼栄養指導3年、調理現場3年、献立作成5年
これまで病院に所属し、主に栄養管理や献立管理を担当してきました。
栄養士コラムは自身の経験も踏まえ、その他、転職や業界情報などみなさんの役に立つ情報発信を行っていきます。
セミナー情報のおすすめ記事
-
2025/11/14
セミナー実施報告:「食品群別荷重平均成分表と食品構成表作成」
-
2024/09/20
セミナーレポート「 ランチ形式で学ぶ在宅での食支援~トリプル改定 医療・介護・在宅のポイント!~」
-
2024/09/24
セミナーレポート 「2024年度食物アレルギーセミナーin神戸 ~共に創ろう 笑顔あふれる 未来~」
-
2024/10/17
セミナーレポート「正しく知ろう!健康食品~健康食品を利用するにあたっての留意点などについて~」